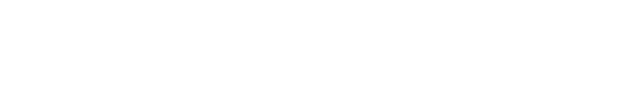腎盂尿管がん
腎臓は、尿を作る実の部分「腎実質」と、尿を貯める部分「腎盂」(じんう)で構成されます。「腎盂」はそのまま「尿管」へとつながっており、尿は「腎盂」から「尿管」の中を流れて「膀胱」まで運ばれます。「腎盂」、「尿管」にできる「がん」が、「腎盂がん」、「尿管がん」です。「腎盂」と「尿管」の境界ははっきり決まっておらず、同じ性質の粘膜で覆われていこともあり、「腎盂がん」と「尿管がん」はまとめて、「腎盂尿管がん」と呼ばれます。いずれも、進行度によって手術療法や薬物療法で治療します。
目次
腎盂尿管がんとは(概要)
「腎臓」は、左右の腰のあたりにある握りこぶしくらいの大きさの臓器です。血液中の老廃物や余分な水分から尿を作って排泄する働きがあります。「腎臓」の中でも尿を作ることを担当する「実」の部分を「腎実質」、「腎実質」で作られた尿を溜めておくことを担当する部分を「腎盂」(じんう)といいます。
2010©︎ Terese Winslow u.s. govt has certain rights
「腎臓」で作られた尿は、いったん「腎盂」にたまり、その後「腎盂」と繋がっている「尿管」という細い管を通ってお腹の下まで流れ「膀胱」にためられます。「膀胱」に尿がたまりトイレで排尿すると、「尿道」を通って尿が体の外に出されます。
もういちど繰り返すと、尿は「腎実質」で作られ、「腎盂」、「尿管」、「膀胱」、「尿道」を通って最後は身体の外に出るわけです。
この中で、「腎盂」、「尿管」、「膀胱」の内側の壁は「尿路上皮」という同じ性質の粘膜で覆われています。
この「尿路上皮」という種類の粘膜に出来るがんを、「尿路上皮がん」と言います。
「尿路上皮がん」は、出来る場所によって「腎盂がん」、「尿管がん」、「膀胱がん」とも呼ばれます。
つまり、「腎盂がん」、「尿管がん」、「膀胱がん」は呼び名は違うけれど、同じ性質を持つ癌、ということになります。
なかでも「腎盂」と「尿管」の境界ははっきり決まっていないことや、どちらも同じ治療が行われることもあり、「腎盂がん」と「尿管がん」は一緒にして、「腎盂尿管がん」や、「上部尿路上皮がん」と呼ばれることもあります。
いっぽう、尿管と膀胱の境界ははっきりしていることや、治療の方法も違うために、「膀胱がん」と「腎盂尿管がん」は別の病気として扱われます。
ただし、もともと同じ「尿路上皮」に発生するがんなので、「腎盂尿管がん」の治療後に「膀胱がん」が出来たり、「膀胱がん」の治療後に「腎盂尿管がん」が出来たりすることは珍しくなく、注意が必要です。
また同じ「腎臓」にありながら「腎実質」と「腎盂」は違う働きをしているため、組織の性質も違います。
よって「腎実質」にできる「腎細胞がん」と「腎盂」にできる「腎盂癌」は、おなじ「腎臓」にできるがんでありながら、性質や治療法は全く違います。
「腎盂癌」は「腎臓」にあるのに、「腎細胞がん」よりも「膀胱がん」に似た性質を持っている、、ややこしいですが、そのような性質があります。
「腎盂がん」、「尿管がん」のいずれも、多くの場合は、見た目に尿が赤くなる「肉眼的血尿」で見つかります。
また一部の「腎盂がん」や、特に「尿管がん」では、がんが大きくなることで尿管の中を塞ぎ尿が流れなくなり、「腎盂」に尿が溜まって腫れ、左右どちらかの腰が痛くなったりします。
「膀胱がん」は、外来診察で行うことのできる「膀胱鏡」という内視鏡検査で診断が可能です。
しかし、「腎盂」や「尿管」は、「膀胱」よりもさらに身体の奥深いところにあるため、そこまで内視鏡を進めて診断するためには入院検査が必要となります。
また「腎盂がん」、「尿管がん」の進行度を調べるために「CT検査」を行ったり、悪性の性質があるかどうかを調べるために「尿細胞診」や「腎盂尿管鏡下生検」などが行われます。
「腎盂がん」、「尿管がん」ともに、一般的に転移がない場合は、がんがある側の「腎盂」を含めた「腎臓」、「尿管」と「膀胱」の一部を摘除する手術を行います。
手術の名前は「腎尿管全摘+膀胱部分切除術」と言います。ほとんどの場合は「後腹膜鏡」という鏡視下手術が行われます。
もしもリンパ節に転移を認めた場合は、抗がん剤治療を行い、リンパ節の転移巣が完全に萎んでなくなればその後に手術を行います。
リンパ節以外の肺、肝、骨などに転移を認めた場合は多剤併用抗がん化学療法を行います。また近年では一部の免疫療法が保険適用となっています。
「腎盂尿管がん」は、同じ「尿路上皮がん」である「膀胱がん」に比べると、その発症頻度は約20分の1程度言われる珍しいがんです。
ところが、年間に「腎盂尿管がん」によって亡くなられる方は、「膀胱がん」よりも多いと言われています。
その理由は、① 腎盂尿管がんは症状が出にくく発見が遅れる ②腎盂・尿管の壁が薄く浸潤、転移をきたしやすい、ためです。
① 症状が出にくく、発見が遅れる、については以下の理由が考えられます。うえでも述べたように、「肉眼的血尿」が一時的に出たとしても、がんが大きくなることで尿管の中を塞ぎ尿が流れなくなり、がんがある側から出るはずの尿はそもそも外へ出なくなります。
すると、その後おしっことして出てくる尿は反対側の腎臓で作られた尿だけだというわけです。
つまり「肉眼的血尿」が一時的に出ても自然におさまってしまうことがあるというわけです。
いっぽう膀胱がんの場合は、尿はかならず膀胱を通って身体の外に出るので、血尿が収まってしまうということが起こりにくいのです。
またがんが大きくなることで腎臓が腫れて「水腎症」になり、左右どちらかの腰が痛くなっても、この痛み自然に治ることもあります。
このように、血尿、腰の痛みなど、腎盂尿管がんのわずかなサインは自然におさまってしまうことが多く、見つかった時にはすでに相当進行していた、となるわけです。
② 腎盂・尿管の壁のうち、一番内側の粘膜は膀胱と同じ性質のものですが、膀胱ではその外側に分厚い粘膜下層や筋肉の層がありますが、腎盂・尿管はこれがとても薄いのです。
ですので、腎盂や尿管の中で大きくなる分にはまだよいのですが、がんの根っこが深く伸びていくと簡単に腎盂や尿管の外に浸潤します。
腎盂尿管癌の症状
「腎盂尿管がん」は、「膀胱がん」と同じように、痛みのない血尿で見つかることが一番多く、これを「無症候性肉眼的血尿」と言います。
まれに健康診断や人間ドックなどの検尿で尿潜血を言われたことがきっかけで見つかることもあります。
気をつけないといけないのは、「腎盂尿管がん」で「無症候性肉眼的血尿」が出たとしても、自然におさまってしまうことがあることです。がんが大きくなることで尿管の中を塞ぎ血尿が流れなくなるためです。
一時的な血尿の原因には「腎結石」、「尿管結石」、「膀胱炎」などの病気もありますが、これらの病気は「腰背部痛」や「排尿時痛」など血尿以外の症状を伴うことが多いです。
痛みのない血尿が出て、自然におさまったとしても、「腎盂尿管がん」の可能性があります。必ず泌尿器科を受診しましょう。
また「腎盂尿管がん」が大きくなることで、尿管の中を塞ぎ尿が流れにくくなり、腎盂に尿が溜まって腫れます。
この状態を「水腎症」と呼び、左右どちらかの腰が痛くなります。
「尿管結石」でも同じように結石が尿管の中を塞ぐことで痛みが出ますが、「腎盂尿管がん」の痛みは「尿管結石」ほどは激しくなく、また自然に治ることもあります。
このように、血尿、腰の痛みなど、腎盂尿管がんのわずかなサインは自然におさまってしまうことが多く、注意が必要です。
もしもこれらのサインを見逃して「腎盂尿管がん」が進行してしまうと、徐々に癌の「根っこ」が深くなります。
特に「尿管がん」は、容易に尿管の壁の外に癌が浸潤して、周囲の組織に浸潤します。
また「腎盂がん」が浸潤すると血流豊富な「腎実質」に浸潤します。やがてがん細胞は血液やリンパ液の流れに乗って全身に広がり、リンパ節や肺、肝臓、骨などに転移します。
こうなると進行した「腎盂尿管がん」の転移巣により、再度腰の痛みが出たり足のむくみなどが出たりします。
このように、泌尿科がんのなかでも「腎盂尿管がん」は予後が悪く、非常に注意が必要な癌です。
上記に当てはまる症状があれば、すぐに泌尿器科を受診しましょう。
とはいえ、最近では、人間ドックの超音波検査で「水腎症」を指摘されて泌尿器科を受診し尿管がんがみつかった、あるいは他の病気の検査で行ったCT検査で「腎盂がん」がみつかった、など、偶然早期で見つかることも増えています。
「腎盂尿管がん」も早期に発見して適切に治療すれば根治できる病気なので、とにかく早く見つけることが大事です。
腎盂尿管がんの検査、診断
「腎盂尿管がん」の診断のためには、「尿検査」、「尿細胞診」、「逆行性腎盂尿管造影」、「尿管鏡検査」、「腹部超音波検査」、「胸部・腹部CT」、「骨盤部MRI」、などを適宜行います。
まずは「尿検査」を行い、「血尿」が出ているかどうかを調べます。
数日前に血尿が出たが今はおさまった、という方でも、「腎盂尿管がん」の方では尿を顕微鏡で確認すると実は血尿続いていることがほとんどです。
ついで「腹部超音波」(エコー)と「尿細胞診」検査を行います。
「腹部超音波」は全く痛みがなく診察室内ですぐに行えるため非常に便利な検査です。
ただし「腎盂尿管がん」のうち、小さなものでははっきり写らないこともよくあります。ただし、一部の尿管癌などは小さくても尿管の流れを塞いでおり、「腎盂」が腫れて「水腎症」になっていることがあります。
「腹部超音波」は、この「水腎症」の存在を確認するのに非常に役立ちます。
「尿細胞診」は「尿検査」で提出してもらった尿の一部を検査に回すことができるため、負担の少ない検査です。
「尿細胞診」で「悪性」という結果がでると「腎盂尿管がん」の可能性は非常に高いのですが「良性」という結果が出ても、必ずしも「腎盂尿管がん」が絶対ないとは言い切れません。あくまで補助的な診断材料となります。
「CT検査」や「MRI検査」を行うことで、かなりはっきりと「腎盂尿管がん」の存在を確認することができます。
かなり小さな腫瘍でも捉えることができますが、これらの検査で写っている腫瘍が本当に悪性の「腎盂がん」あるいは「尿管がん」かどうかは確定できません。
まれではありますが、「腎盂」や「尿管」に良性の腫瘍ができることもあり、これらは 「CT検査」や「MRI検査」で「がん」と区別ができません。また何らかの原因で腎盂や尿管が出血して血の塊があった場合も、CT検査では腫瘍との区別がつきづらくなります。
「腎盂尿管がん」と確定診断するためには2つの方法があります。
1つは「逆行性腎盂尿管造影」です。
「逆行性腎盂尿管造影」は、まず「膀胱鏡」を使って膀胱の中を観察しながら、膀胱の中にある小さな尿管の出口へ細いカテーテルを入れ、腫瘍の周囲に「造影剤」を注入する検査です。
「腎盂尿管がん」の腫瘍の部分が影になってレントゲンで写ります。そしてその周囲から採取した尿を「尿細胞診」に提出し「悪性」となれば「腎盂尿管がん」と確定します。
もう1つは、「尿管鏡検査」と「尿管鏡下生検」です。
「尿道」、「膀胱」、「尿管」、「腎盂」と尿の流れにさかのぼる形で、細い内視鏡を進めて、「腎盂尿管がん」の腫瘍を直接カメラで観察し、腫瘍の組織を一部採取して病理検査で悪性かどうかを調べます。
これで悪性と診断されれば、「腎盂尿管がん」と確定します。
上記のいずれの検査で診断がつけばもう片方は行わないこともあります。段階的にどちらを先に行うかは、その時の状況によって異なります。
「腎盂尿管がん」と確定すれば、がんの浸潤度(根の深さ)や転移がないかをを調べるために、「胸部CT検査」、「骨シンチグラフィー」、「PET」などを行い、治療方針の参考とします。
腎盂尿管がんの治療
①転移を認めない場合
「腎盂がん」、「尿管がん」ともに、転移がない場合は、がんがある側の「腎盂」を含めた「腎臓」と「尿管」、「膀胱」の一部を摘除する手術を行います。
手術の名前は「腎尿管全摘+膀胱部分切除術」と言います。ほとんどの場合は「後腹膜鏡」という鏡視下手術が行われます。
「腎盂がん」なら「腎盂」だけ、「尿管がん」なら「尿管」だけ摘出したらよいのでは、と思うかもしれませんが、以下に説明する理由であまり良くないとされます。
「腎盂がん」の手術で、「腎盂」と「腎実質」を切り離して「腎盂」だけを取り除くことはそもそも手術として無理です。
もしも「腎盂」がなくなると「腎実質」で作られた尿の行き場症がなくなり、背中のなかで体内に漏れてくることになるため、「腎臓」を「腎実質」と「腎盂」もろとも摘出する必要があります。
またそうすると、もともと「腎盂」につながっていた「尿管」が残ります。
「腎盂」「尿管」「膀胱」は同じ「尿路上皮」で覆われているので、残った「尿管」の中に、摘出した「腎盂がん」と同じような性質の「尿管がん」が再発する可能性は十分あり得ます。
それならば「腎臓」がなくなって無用となる「尿管」は一緒にに取ってしまった方が良いだろう、という考えです。
「尿管がん」の手術で、「がん」のある部分の尿管を一部とってまたつなぎ合わせる手術は、やろうと思えば無理なことはありません。
事実、腎臓がなんらかの理由でもともと1つしか残っていない方で、その残った「腎臓」に繋がった「尿管」に小さな腫瘍ができた場合は、その部分だけを摘出してつなぎ合わせることがあります。
ただしこのような場合でも腫瘍が大きく摘出する部分の尿管長が長い場合はつなぎ合わせるのが無理なこともあります。
ただし、摘出した尿管を切り取った端の部分から同じような「尿管がん」が再発し、不幸な経過を辿ることが多いため、「尿管」を全て摘出するのが標準治療となっています。
「尿管」を摘出すると「腎臓」から尿を運ぶことができなくなるため「腎臓」も一緒に摘出します。「腎臓」を提出する理由は「腎盂」にがんが再発するのを防ぐ意味合いもあります。
「尿管」と「膀胱」の境い目は「尿管口」と言います。比較的はっきり境い目としてわかるのですが、それでも「腎盂」、「尿管」「膀胱」は同じ性質の「尿路上皮」で覆われています。
「尿管がん」で「腎臓」と「尿管」摘出した後に、「尿管口」に「がん」が再発することがあります。そこで、「尿管口」をくり抜く形で「膀胱」も一部摘出し、開いた穴を縫い合わせて「膀胱」を閉じます。
以上の理由から、「腎盂がん」、「尿管がん」の根治手術は、「腎尿管全摘+膀胱部分切除術」になるのです。
このうち、「腎臓」と「尿管」を摘出するパートは、昔は腰の部分を斜めに30cm程度切開するか、お腹の真ん中を同じく30cmくらい切開して、「開腹手術」として行われていました。
ここ20年くらいはほとんどが「後腹膜鏡手術」という、お腹の中に内視鏡を入れて行う手術で行われています。これにより1cm程度の創が数個と下腹部に7cm程度の創が残るだけで手術を行えるようになりました。
また、これまで主に前立腺がんや腎細胞がんの治療に対して行われてきた、手術用ロボット「DaVinci」を使った、「ロボット支援」手術が、2022年4月から「腎盂がん」「尿管がん」の根治手術にも保険適用となりました。
今後はこちらに置きかわっていく可能性があります。
② 転移を認める場合
「腎盂尿管がん」の癌細胞が、血液やリンパ液の流れに乗って全身に広がり、リンパ節や肺、肝臓、骨などに転移ている場合があります。
このような時は、手術で摘出しても全てが取り切れるわけではないため、「全身薬物療法」が必要になります。
「全身薬物療法」には「抗癌剤」の点滴治療をします。また「抗癌剤」で治療しても無効な場合は、「免疫チェックポイント阻害薬」の点滴治療があります。
腎盂尿管がんの予防、注意点
喫煙者は尿路上皮癌になりやすいと言われていますので注意が必要です。
「腎盂尿管がん」は、同じ「尿路上皮がん」である「膀胱がん」に比べると、予後が悪いとされます。「
肉眼的血尿」や「腰背部痛」などの症状がが一時的に出たとしても、がんが大きくなることで、そのような腎盂尿管がんのわずかなサインが自然におさまってしまうことがあり、進行した状態で見つかることが多いがその理由の1つです。
痛みのない血尿が出て、自然におさまったとしても、「腎盂尿管がん」の可能性があります。必ず泌尿器科を受診しましょう。
また、「腎盂尿管がん」で「腎尿管全摘+膀胱部分切除術」を行い、根治できたとします。
その場合でも、「腎盂がん」、「尿管がん」、「膀胱がん」は呼び名は違うけれど、同じ性質を持つがんということを忘れてはいけません。
同じような性質の「膀胱がん」ができていないかを定期的な「膀胱鏡検査」の検診でチェックする必要があります。必ず主治医の指示に従い、定期通院を行い検診を受けましょう。